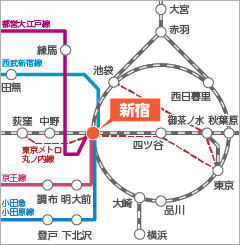税務調査と国税の犯則調査の関係
1 税務調査と犯則調査の意義
(1)税務調査
税務調査は、税務当局が更正・決定の課税処分やその他の処分等を行うために証拠資料の収集等を行う手続です。
税務調査における質問検査権(国税通則法第7章の2)は、相手方の承諾を得て行われる任意調査に限られており、それ以上の強制的な手続は認められていません。
もっとも、税務調査は、不答弁や虚偽答弁等に対する罰則(国税通則法128条2号、3号)が定められており、間接強制により実効性が担保された手続となっています。
税務調査は租税の公平確実な賦課徴収のために必要な資料の収集を目的とする行政手続である
判例(最高裁昭和47年11月22日大法廷判決)は、税務調査の質問検査権について、租税の公平確実な賦課徴収のために必要な資料の収集を目的とする手続であって、その性質上、刑事責任の追及を目的とする手続ではないとしています。
また、質問検査の結果、租税逋脱の事実が発覚する可能性があるとしても、質問検査が、実質上、刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有するものと認めるべきことにはならないとしています。
(2)犯則調査
国税の犯則調査は、税務当局が国税に関する犯則事件を対象として犯則事実の有無を解明するために行う手続です。
国税局の査察部が所得税や法人税などの脱税事件を対象として行う査察調査は、国税の犯則調査の代表例です。
犯則調査では、質問や検査などの任意調査(国税通則法131条)のほかに、裁判官の発する許可状により、臨検、捜索及び差押えの強制調査(国税通則法132条)を行うことができます。
なお、犯則調査については、不答弁や虚偽答弁、検査の拒否等に対する罰則の定めはありません。
犯則調査は、行政手続であって刑事手続ではないが、特別の捜査手続としての性質を帯有する
判例は、犯則調査の性質について、一種の行政手続であって刑事手続ではないとしています(最高裁昭和44年12月3日大法廷決定)。
また、犯則調査は、国税の公平確実な賦課徴収という行政目的を実現するための手続ですが、実質的に租税犯の捜査としての機能を営むものであり、特別の捜査手続としての性質を帯有するものとされています(最高裁昭和59年3月27日判決)。
2 税務調査と犯則調査の関係
税務調査の質問検査権を犯則調査や犯罪捜査の手段として行使してはならない
国税通則法は、税務調査のための質問検査権について、犯罪捜査のために認められたものと解してはならないと定めています(国税通則法74条の8)。
この規定は、税務調査などの行政調査の権限は、所定の行政目的のため行使されなければならず、税務調査に藉口して犯罪捜査のための証拠資料を収集することは憲法35条、38条の趣旨に照らして許されないという、当然の事理を明確化したものと考えられています。
この点に関して、判例(最高裁平成16年1月20日決定)は、税務調査の質問検査権について、犯罪の証拠資料を取得収集し、保全するためなど、犯則事件の調査あるいは捜査のための手段として行使することは許されない旨を判示しています。
税務調査の質問検査権を犯則調査や犯罪捜査の手段として行使することは違法となり、そのような方法で取得された証拠資料については、告発後の刑事訴訟において証拠能力が否定される可能性があると考えられます。
適法な税務調査で取得収集された証拠資料を犯則調査で利用することは一定の範囲で許容される
それでは、税務調査の質問検査権を犯則調査や犯罪捜査の手段として行使していない場合(税務調査が適法に行われた場合)において、税務調査で取得収集された証拠資料を犯則調査で利用することはできるでしょうか?
この点に関して、判例(最高裁昭和51年7月9日判決)は、税務調査中に犯則事件が探知された場合に、それを端緒として犯則事件としての調査に移行することは許されるという、原判決の判断を認めています。
判例は、税務調査で判明した事実関係を端緒として犯則調査に移行することは許されるとしていることから、捜索や差押えの必要性を明らかにする疎明資料とするなど、犯則調査を開始するために必要な限度で、税務調査で取得収集された証拠資料の一部を利用することは認められると考えられます。
さらに、判例(最高裁平成16年1月20日決定)は、税務調査の質問検査権の行使にあたって、取得収集される証拠資料が後に犯則事件の証拠として利用されることが想定できたとしても、そのことによって直ちに、質問検査権が犯則調査あるいは犯罪捜査のための手段として行使されたことにならない旨を判示しています。
判例は、税務調査で取得収集される証拠資料が後の犯則事件で利用されることが想定できたとしても、質問検査権の行使が違法になるものではないとしており、税務調査で取得収集された証拠資料を犯則調査で利用することについて一定の範囲で許容しているものと考えられます。
犯則調査で収集された資料を利用して課税処分を行うことは認められる
それでは、犯則調査で収集された資料を課税処分に利用することはできるでしょうか?
この点について、判例(最高裁昭和63年3月31日判決)は、収税官吏が犯則調査を行った後に、税務署長が当該犯則調査により収集された資料を利用し、税務調査(国税通則法24条)を実施したうえで更正処分等を行った事案において、犯則調査により収集された資料を課税処分等に利用することは許される旨を判示しています。
判例は、正当な犯則調査により収集された資料を基礎として課税処分を行うことを認めていると考えられます。
3 まとめ
税務調査と犯則調査の関係について、判例は、税務調査の質問検査権を犯則調査の手段として行使することは許されないとしていますが、適法な税務調査で取得収集された証拠資料を犯則調査で利用することを一定の範囲で許容していると考えられます。
税務調査と犯則調査は、いずれも租税の公平確実な賦課徴収を目的とする行政手続ですが、調査の方法や機能には違いがあり、それぞれの調査の関係を踏まえたうえで対応していくことが重要となります。
関連記事はこちら
過少申告加算税における「更正の予知」と「正当な理由」
脱税とは?脱税したらどうなる?脱税事件の類型と刑事告発の状況
関連業務はこちら