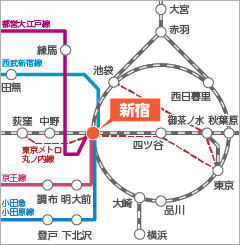事業所得と他の所得はどのように区別されるか?
1 所得税法における所得の分類
所得税法は、個人の収入等の所得をその性質に応じて10種類の所得に分類したうえで、所得の種類ごとの計算方法を定めています。
これは、所得が源泉や性質によって担税力(税金を負担する能力)が異なることから、所得を分類してその種類に応じた計算方法を定めることにより、担税力に即した公平な課税を図るものと考えられています。
この所得分類の趣旨について、裁判例(東京地裁平成25年9月27日判決)は、「所得がその性質や発生の態様によって担税力が異なるという前提に立って、公平負担の観点から、各種の所得について、それぞれの担税力に応じた計算方法を定め、また、それぞれの態様に応じた課税方法を定めるために、所得をその源泉ないし性質によって10種類に分類している。」としています。
所得税法では、所得の分類によって、所得の計算方法や課税方法が異なることから、個人の経済活動により生じた所得がどの種類の所得に分類されるかの判断は、納税者の税額に影響を与える重要な問題といえます。
以下では、実務において問題となることの多い事業所得と他の所得の区別についてみていきます。
2 事業所得とは?
(1)事業所得の意義
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得をいいます(所得税法27条1項)。
上記の委任を受けて、所得税法施行令63条は、事業所得を生じる「事業」の種類を定めるとともに(同条1号~11号)、前各号に掲げるもののほか、対価を得て継続的に行う事業も「事業」に含まれる旨を定めています(同条12号)。
(2)事業所得を生じる「事業」の判断基準
所得税法は、事業所得を生じる「事業」の具体的な定義を示していないことから、これまでの裁判例は、「事業」の解釈にあたり考慮すべき要素を挙げています。
裁判例(福岡高裁昭和54年7月17日判決)は、所得税法27条1項、同法施行令63条の規定によれば、事業所得とは「対価を得て継続的に行う事業から生ずる所得」を指称するとしたうえで、ここにいう「事業」とは、「社会通念に照らし事業と認められるもの、すなわち個人の危険と計算において独立的に継続して営まれ、かつ事業としての社会的客観性を有するものと解すべきである」と判示しています。
他の裁判例(名古屋地裁昭和60年4月26日判決)は、一定の経済的行為が、対価を得て継続的に行う事業(所得税法施行令63条12号)に該当するか否かは、「当該経済的行為の営利性、有償性の有無、継続性、反覆性の有無のほか、自己の危険と計算による企画遂行性の有無、当該経済的行為に費した精神的、肉体的労力の程度、人的、物的設備の有無、当該経済的行為をなす資金の調達方法、その者の職業、経歴及び社会的地位、生活状況及び当該経済的行為をなすことにより相当程度の期間継続して安定した収益を得られる可能性が存するか否か等の諸要素を総合的に検討して社会通念に照らしてこれを判断すべきもの」と判示しています。
裁判例によると、個人の経済活動が事業所得を生じる「事業」に該当するかどうかは、裁判例が指摘する様々な要素を総合的に検討したうえで、最終的には社会通念に照らして判断されることになります。
また、裁判例で示されている様々な要素は、事業所得と他の所得を区別する場合における重要な判断基準となります。
例えば、事業所得と給与所得の区別が問題となる場合には、自己の危険と計算、独立性が重要な判断基準になります。また、事業所得と雑所得の区別においては、営利性や継続性、事業としての社会的客観性の有無が重視されると考えられます。
(3)事業所得にならない所得
山林所得と譲渡所得に該当するものは事業所得に含まれない
事業から生じる所得であっても、山林所得又は譲渡所得に該当するものは、事業所得から除かれています(所得税法27条1項括弧書)。
具体的には、山林事業による所得のうち、所有期間が5年を超える山林の伐採又は譲渡による所得は、山林所得に該当し(所得税法32条1項、2項)、事業所得には含まれません。所有期間が5年以内の山林の伐採又は譲渡による所得は、事業所得(事業に至らない場合は雑所得)になります(所得税法33条2項2号参照)。
事業に関連する資産の譲渡のうち、事業用の固定資産(所得税法2条1項18号)の譲渡(反復継続して譲渡される場合を除く)による所得は、譲渡所得に該当し(所得税法33条1項)、事業所得に含まれません。棚卸資産(所得税法2条1項16号)の譲渡による所得は、事業所得になります(所得税法33条2項1号参照)。
不動産などの貸付業から生じる所得は事業所得にならない
不動産の貸付業又は船舶もしくは航空機の貸付業に該当するものは、事業所得を生ずる「事業」から除かれており(所得税法施行令63条柱書括弧書)、これらの貸付業から生じる所得は不動産所得となります(所得税法26条1項)。
事業上の資金の運用による利子や配当は事業所得に含まれない
事業に関係する所得であっても、事業資金の預貯金による利子や事業上の保有株式の配当は、それぞれ利子所得(所得税法23条1項)や配当所得(所得税法24条1項)に該当し、事業所得には含まれません(利子所得について東京地裁平成5年10月29日判決参照。配当所得について名古屋高裁金沢支部昭和49年9月6日判決参照)。
3 事業所得と給与所得の区別
(1)給与所得の意義
給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいいます(所得税法28条1項)。しかし、「これらの性質を有する給与」を具体的に判断する基準は、条文上、明らかではありません。
一方、事業所得を生じる「事業」は、様々な要素を総合的に検討したうえで、最終的には社会通念に照らして判断されることになります。
そのため、業務の遂行または労務の提供を内容とする経済活動から生じる所得について、事業所得と給与所得のいずれに該当するかの判断が困難な場合、事業所得と給与所得を区別する判断基準が問題となります。
(2)事業所得と給与所得の取扱いの差異
事業所得と給与所得は、下記のとおり、計算方法や課税方法に差異があります。
具体的には、事業所得の場合、必要経費の実額控除が原則となり(所得税法37条1項)、確定申告が必要となりますが、給与所得に該当する場合、給与所得控除(概算控除)が適用されるとともに(所得税法28条2項)、一般的に源泉徴収の対象となります(所得税法183条1項)。
また、消費税法における事業者が、他の者から役務の提供を受けたことによる対価として、事業所得に該当する給付(例:外注費)を支払う場合には、仕入税額控除(消費税法30条1項)の対象となりますが、給与所得に該当する給付(例:給料)を支払う場合には、課税仕入れにあたらず(消費税法2条1項12号参照)、仕入税額控除は認められません。
このように、事業所得と給与所得は計算方法等に差異があることから、事業所得と給与所得の区別は、納税者の利害に影響を与える重要な問題となります。
(3)事業所得と給与所得を区別する判断基準
事業所得と給与所得の区別について、判例(最高裁昭和56年4月24日判決)は、判断の一応の基準として、「事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得」であるとしています。
これに対し、「給与所得とは雇傭契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付」であるとしています。そして、「給与所得については、とりわけ、給与支給者との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給されるものであるかどうかが重視されなければならない」としています。
判例によると、事業所得と判断されるには、独立性を有しており、自己の計算と危険において営まれる業務から生じる所得であることが必要であるといえます。自らの経済活動によって収入が左右され、損失のリスクを負担することなどが考慮されることになります。
一方、給与所得は、非独立的であり、従属的な労務の対価としての性質を有する所得とされます。収入がある程度定められていて、自らの経済活動による損失のリスクを負担しないことや、一定の空間的、時間的な拘束を受けて労務を提供することなどが重視されることになります。
主な裁判例としては、弁護士の顧問料収入を事業所得としたもの(上記最高裁昭和56年4月24日判決)、電力会社の委託検針員が受領した委託手数料を事業所得としたもの(福岡地裁昭和62年7月21日判決)、民法上の組合の組合員が組合の事業に従事して支払を受けた収入を給与所得としたもの(最高裁平成13年7月13日判決)などがあります。
4 事業所得と雑所得の区別
(1)雑所得の意義と範囲
雑所得とは、利子所得から一時所得までの9種類の所得のいずれにも該当しない所得であり(所得税法35条1項)、①公的年金等(同条2項1号)と②それ以外の雑所得(同条2項2号)の合計となります。
②それ以外の雑所得(以下、単に「雑所得」といいます)は、他の所得に分類されなかった種々の所得の受け皿としての類型であり、具体的な定義は示されていません。
課税実務では、雑所得を、業務に係る雑所得(所得税基本通達35-2)とその他雑所得(所得税基本通達35-1)に分類しています。
(2)事業所得と雑所得の取扱いの差異
事業所得と雑所得は、原則として計算方法は同じですが、雑所得は、事業所得と異なり、計算上の損失を他の所得と損益通算することはできません(所得税法69条1項参照)。
また、事業所得を生じる業務を行う者には、青色申告が認められており(所得税法143条)、青色申告特別控除(租税特別措置法25条の2)などの各種の特典が与えられていますが、雑所得を生じる業務を行う者には青色申告は認められていません。
このように、事業所得と雑所得の区別は、納税者の利害に密接に関係しており、営利を目的とした経済活動による所得について、事業所得と雑所得のいずれに該当するかの判断が困難な場合、事業所得と雑所得を区別する判断基準が問題となります。
(3)事業所得と雑所得を区別する基準
事業所得と雑所得の区別については、上述の裁判例(福岡高裁昭和54年7月17日判決、名古屋地裁昭和60年4月26日判決)によると、個人の経済活動が事業所得を生じる「事業」に該当するかどうかにつき、様々な要素を総合的に検討したうえで、社会通念によって判断されることになります。
具体的には、ある所得を得るための経済活動が、営利性や継続性、事業としての社会的客観性、収益の安定性を有しており、社会通念に照らして「事業」といえる場合には、当該所得は事業所得に区分されますが、「事業」といえない場合には、当該所得は雑所得となります。
課税実務でも、事業所得と雑所得の区別は、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するとされています。
もっとも、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存が無い場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く)には、業務に係る雑所得に該当するとされています(以上、所得税基本通達35-2(注))。
5 まとめ
所得税法における所得分類は、所得の種類に応じた計算方法を定めることにより、担税力に即した公平な課税を図るための仕組みです。
所得分類には、各種所得の計算方法の差異に着目した所得の種類の変更により、税負担の軽減や回避を図る行為を誘発する側面がありますが、納税者としては、収入等の実態を踏まえて、所得の区別をすることが重要となります。
関連業務はこちら:税金に関わる法務